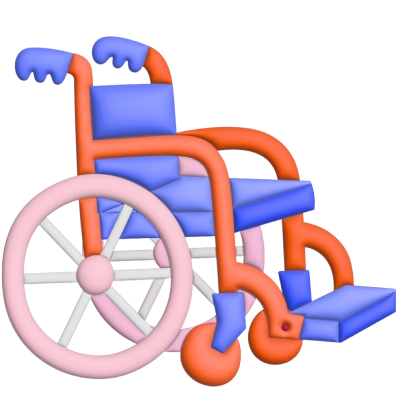 VOICE OF
VOICE OF
(BOSAI) ACTION
障がい者
QUESTION VOICE
チャロさん
高校生の頃の交通事故の怪我により、歩行障害が残り車椅子利用者に。現在は都内に在住。災害に対する関心は近年あがっており、ハザードマップで危険性を確認してみたこともあるそう。
これまでに被災経験がないため、ネットニュースで災害に関する報道をみるたびに「自分は避難できるのか」「避難所の生活はどうなるのか」と漠然と不安になることも多いそうです。
さまざまな障がいをもつ方がおり、災害に対する不安や気になることには微細なグラデーションがあるという前提のものと、今回の第1回には、肢体障がいのある車椅子利用者の方にご協力いただきました。
ADVICE VOICE
松川杏寧 准教授
防災・災害分野の研究機構で複数のポストを歴任した後、2023年から兵庫県立大学の減災復興政策研究科で准教授を務める、防災・減災のスペシャリスト。
今年発生した能登半島地震でも、被災地で災害時要配慮者への支援活動を続けています。
自分で避難できるかが心配です
とにかく「自力で逃げられない可能性」があることが、大きな不安です。自宅に留まることになるのか、避難所に向かうのか、その場合はどこに連絡をすればいいのかもいまいちわかっていません。
また、子どものいる方はさらに大変だと思います。たとえば、在宅勤務中に自分と子どもしか家にいない状態で避難しなくてはならなくなったとき、もしもマンションのエレベーターが止まってしまったら本当にどうしよう、という懸念も聞きました。
災害・防災に関してはまわりの人と積極的に話したりせず、どうしても優先度が下がってしまいがちなので、もう少し普段から考えないとな、と思いました。
災害時に自分が取れる選択肢にはどのようなものがあるのかを自分で把握・整理し、避難計画・避難生活計画を立てます。大前提として「自分の命を守るために危険な場所から安全な場所に移動する」という行為の避難行動と「家に帰れないため、避難生活を送るためにどこに行き・どう生活するか」の避難、この2つは混同されやすいのですがまったく別です。命を守るために向かう場所と、避難所と指定されている所がイコールかもしれないし、そうではないかもしれません。
災害が起きたときに自分の命を守るためにどう行動すべきかを考えるのが、避難行動の計画。命が守られたあとの次のステップとして、自宅に戻るのか・避難所で生活をするのか・どこかに身を寄せるのかという、避難生活の計画を考えます。
自分は一人で避難できるのか、誰かの助けが必要なのか、災害時に自分が取れる選択肢はどのようなものがあるのかを踏まえて、避難計画・避難生活計画を具体的に考えていきます。自分一人で計画を立てるのが難しい場合には、障がいをもっている方は地域の「相談支援専門員」さんに相談してみましょう。
災害が起きたときにどんなリスクが発生するのか、普段の生活にどんな変化がでるのかを一緒に考えてもらいます。たとえば、風水害が起きるとします。「川が決壊して水が流れ込んできます。あなたの家は1.5メートル浸水します」というのがハザードマップから得られる情報です。でも肝心なのは「じゃあ、1.5メートル床上浸水すると、私の家はどうなる?私の生活はどうなる?」というポイント。
「1.5メートル弱床上浸水すると、あなたの家は2、3週間は住めないよ。その間、どうする?」「その間、飲んでる薬はどうする?」など。精神障がいの方で、普段飲んでいる薬を一度に数週間分はもらえないこともあるでしょう。その場合、先生に薬をもらいにいくことを考えると、最適な避難先はどこになるのか。
また、ご自宅で動かせないような機器を使って日常生活を自立しながらおくっていらっしゃる方の場合は、それらをもって避難できるのか、地域の小学校で避難生活をおくれるのか、できない場合にはどこにいくか。普段から関わりのある事業所・団体・施設で受け入れてもらえるところはあるのか。車椅子利用者で運転をする方においては、災害時は車が走れない可能性が高いとすると、どうするか。
そうやって一つひとつ噛み砕いていってはじめて、具体的な備えを考えるステップに進めます。
そして「いざというときに、本当にその避難先にいけるのか」を確かめるために、計画を立てたら一度、実際に避難訓練をしてみることをおすすめします。たとえば家族や親戚、友人の家を考えているのであれば、避難訓練の際に実際に「いまから避難の練習で行ってみようと思うんだけど」と連絡をして実施してみる。
自分でつくる「安心防災帳」を使って整理してみるとわかりやすいと思います。
これは、備え(=自分に使える資源)と自分がもっている選択肢を整理し、なにがどのくらいあるのか、どこが足りていないのかを自分で見つけるお助けツールです。
自分でつくる安心防災帳
https://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/suzurikawa/skit_02.html
自分はいまどのような健康状態で、どのように生活していえるのかを確認し、現在ある備え、必要となる備えをわかりやすく整理できる防災帳。無料PDFをダウンロード、印刷が可能です。
この安心防災帳は、ICF(国際生活機能分類)*基準でつくられています。
*健康状況を把握するために用いられる。人間の健康状態や心身の機能、環境による評価をアルファベットと数字で表す世界共通の分類方式。
防災グッズだけでなく、薬や必要な飲食物といったものが、たとえば自宅以外の場所で1週間避難生活するとなったら足りる量があるのか、ないのか。
自分がもっている資源と選択肢を整理したら、災害時に自分がより安全安心に生活するために、自分のレジリエンスを高めるためにどうやってこの備えを増やすかという計画が立てられます。
障がい者の方は、普段から通っている就労事業所や支援者団体を通して繋がっているコミュニティの人とお互いに支え合うという話はよく聞きます。
災害のときには「どこに避難しよう・身を寄せあおう」というのを決めておくのもよいでしょう。もし取り決めた施設団体が被害をうけて集まれない場合には「隣町のどこ」といったように第2、第3まで決めておく。いざというときに頼れる口を確保しておくことがキーになってきます。
個別の避難計画の立てかたについて詳しくは、ぜひこちらもお読みください。
▶︎防災リテラシーって?「私」の避難計画の立てかた
https://bosaivoice.com/professor/1/
一般の方と同じ環境で迷惑をかけずに生活できるか、不安です
避難所生活においては、車椅子ユーザーの自分が、みなさんと同じ環境で迷惑をかけずに生活できるか不安です。避難所が(たとえば段差などが取り除かれた)バリアフリーかどうかはわかりません。もし古い校舎の体育館とかだと、車椅子での移動が難しい、といったこともあるんじゃないかな...。
大きな不安としては、まわりからも聞くのが褥瘡(じょくそう)* や排泄に関すること。このあたりの支援をしてもらえるのかどうか。あとは出入りのしやすい位置などに自分のスペースを確保することができるのか、など、考えればキリがないです。周りの人に迷惑をかけてしまわないかも気になります...。福祉避難所** にも入れるかわからないですよね。
*褥瘡(じょくそう)とは、寝たきりなどにより体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ったりすることで、皮膚の一部がただれたり、傷ができてしまうこと。身体の麻痺、肢体障害によって、自身で身体を動かせない・寝返りがうてない人に起こりやすい。
**福祉避難所 福祉避難所とは、お年寄りや障害がある人・妊婦や乳幼児といった災害時要配慮者とその家族を受け入れる避難所のこと。ただし避難所には限りがあり、また通常は一般の避難所で振り分けをおこない、そこで福祉避難所に行ける人がきまる。
やはり健常者のほうが避難は早いので、(障がい者である)自分がついたころには満杯で、入口の靴によって施設内に車椅子で入れずに困った、ということは聞きます。
あとは、視覚・聴覚に障がいをもち、認知やコミュニケーションに困難がある場合に、みんなと一緒に避難所にはいったものの、伝えられている情報がわからずに、医薬品や食糧の物資配布のこともわからず、自分がいまどういう状況なのかもわからず、安心・安全な生活を送れないといった課題はよく挙がります。特に、(聴覚障がいは周りからそうだとわかりづらいため)ただ挙動不審に見えてしまい周囲から距離を取られてしまう・うまくいかない、といったこともあると聞きます。
ここで一つ備えとして役立つのは、障がいのことを隠しているわけではなければ、地域の避難訓練などに顔をだし、自分の存在を地域の人に知っておいてもらう、ということが役立ちます。自分の存在と状況を知っておいてもらい、いざというときに周りのかたからの支援をスムーズにする、ということです。
障がいをもつかたは、その種類によっても生活状況によってもかなり細分化されます。先に話した「自分でつくる防災帳」は、自分には現状、災害に備えてどんな資源(使えるおの)と選択肢があるのかを整理できるものですが、なにによって避難行動が阻害されるのかも把握できます。
たとえば、
・自分の足では歩けない、移動手段がないため「避難所までの避難が難しい」
・車椅子を押してくれる人がいない
・視覚障がい、聴覚障がいによって認知に問題があり、命に関わる情報を把握できない
・精神障がいによって、情報が把握できない・コミュニケーションがうまく取れないため、避難行動に困難がでる
など。
後者の場合、近所やまわりに「避難するための情報」をヘルプしてくれる方、コミュニケーションが困難であることを知ったうえでヘルプしてくれる方がいると、改善されそうですよね。
いざというときには「お隣さん・近所の人にしか頼れない」けれど「話したことがない(自分がどのような状況か知ってもらっていない)」。声をかけてもらう可能性も低く、自分から助けを求めるのも難しいでしょう。避難先がわからず、それを聞きにいくこともできない、といったことに陥ってしまいます。
自分の身を守るための資源として「人間関係」が重要になる場合があります。たとえば買い物にいくときに出くわせば「こんにちは」と挨拶をするくらいでもいいんです。ご近所さんとの対人関係をあいさつをする程度でももっておく、というのは大きな備えになります。
ただ、精神障がいの方には、生活する地域内ではご自身の障がいを公にしないで暮らしている方も一定数います。普段の繋がりとしては、福祉サービスや同じような障がいを抱えた方とのコミュニティがあり、生活はそのネットワークで完結してることが多いです。しかし、お互いに物理的に近所には住んでおらず、いざというときに頼れるのは自分のご近所さんしかいない、といったこともあり得ます。
自分一人でご自身の存在をまわりに伝えていくことが難しい場合には、民生委員に協力してもらって働きかける方法もあります。
ほかに知っておくとよいこと
(BOSAI VOICE制作チーム)ほかにも、当事者、また支援者が知っておくとよいことがあれば、教えてください。
障がい者の方においては、各地域に当事者団体や自立支援協議会があります。地域をまたいで団体同士で繋がることで、中長距離の支援ネットワークとして、被災地だけではまかなえない部分に対して支援できることもあります。
また、障がい者の方においては、かなりの難病にもかかわらず難病指定を受けていない・障害者手帳をとっていない、といったケースも結構あるんです。となると、地域の人からは“困難が見えてない”状態になってしまっている。そういった人たちについては、やはり地域内でケアする限度がどうしてもあるので、やはり行政にちゃんと繋いでいく必要があります。
災害対策、避難所運営会議*において、議題にあげてもらうためにも、やはり地域の人にある程度、ご自身のことを知っておいてもらうと、有事の際のコミュニケーションや連携はつくりやすいです。
*避難している人を中心にどうやってその集団生活を協力して乗り切るのかを考えるための会議。
一般的に、自治会・町内会など「避難所運営マニュアル」を作った役員の人たちが主体となります。
日本の要配慮者支援は基本的に手挙げ方式なので、やはりご自身から「私はこういう状態であるため、こんな支援が必要です」と伝えて支援を要請することが必要ですが、やはり自ら手挙げすることが難しい方は一定数いらっしゃるんです。
手挙げ方式でどんな人が地域にいてなにができるのかを考えていくのは一つの正規ルートとしつつ、どうすれば、個人的なセンシティブな情報を自己開示しなくても支援が受けられる状況になっていけるのかが課題だと思っています。
個別の避難計画の立てかたについて詳しくは、ぜひこちらもお読みください。
▶︎防災リテラシーって?「私」の避難計画の立てかた
https://bosaivoice.com/professor/1/
ADVICE VOICE

松川杏寧 准教授
1984年生まれ。同志社大学大学院社会学研究科で博士の学位取得後、人と防災未来センター、防災科学技術研究所を経て現職。
専門は犯罪社会学、福祉防災学。2011年の東日本大震災までは環境犯罪学による犯罪予防について研究していたが、3.11以降災害の分野へ。
地域住民による犯罪予防や災害時要配慮者の防災対策、避難所研究など、地域コミュニティや脆弱性の高い人々を主な研究の対象としている。