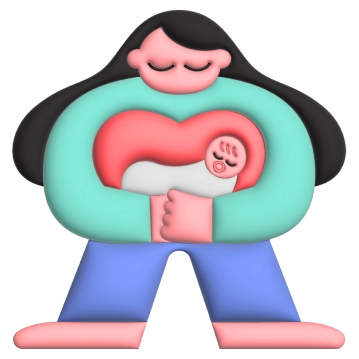 VOICE OF
VOICE OF
(BOSAI) ACTION
妊産婦さん・お母さん
QUESTION VOICE
ササキさん
東京都在住。3歳と1歳の2児の母。防災キットはベーシックなものを「一応持っている」。
そこに、おむつや子どもの好物であるアンパンマンカレーなど個別の準備をしている。
アヤさん
東京都在住。現在、妊娠6ヶ月。防災への備えに関しては「正直ほとんどなにもしていない」とのこと。
ADVICE VOICE
松川杏寧 准教授
防災・災害分野の研究機構で複数のポストを歴任した後、2023年から兵庫県立大学の減災復興政策研究科で准教授を務める、防災・減災のスペシャリスト。
今年発生した能登半島地震でも、被災地で災害時要配慮者への支援活動を続けています。
指定避難先まで“たどり着ける?
1歳の子は自分で歩けないのでその子を抱えて、さらに3歳の子も連れて、防災グッズを入れたリュックをもって...なんて、実際にはどれほど現実的なんだろう、と考えます。
地震が大きいと、道にもガラスの破片などが散乱して危ないとも聞きましたし...。
あと「そもそも避難先は地域の小学校でいいんだっけ」とか。咄嗟にどこに逃げたらいいのかその時に正しく判断できるのか、不安です。
特に昼間の時間で旦那が家におらず、一人で避難するとなったら、ちゃんと防災キットや必要なものをもって避難できるのか、不安です。そもそも急いで行動すること自体が大変で...。やっぱり身体の重さとかもそうですし、地面にあるものも見えづらい。
あと、どこに避難したらいいのかも知らないことに気づいたので、ちゃんと調べなきゃと思いました。もしも妊娠後期の時期に震災が起きて避難することになったら、と考えると、不安になります。
災害時に自分が取れる選択肢にはどのようなものがあるのかを自分で把握・整理し、避難計画・避難生活計画を立てます。大前提として「自分の命を守るために危険な場所から安全な場所に移動する」という行為の避難行動と「家に帰れないため、避難生活を送るためにどこに行き・どう生活するか」の避難、この2つは混同されやすいのですがまったく別です。命を守るために向かう場所と、避難所と指定されている所がイコールかもしれないし、そうではないかもしれません。
災害が起きたときに自分の命を守るためにどう行動すべきかを考えるのが、避難行動の計画。命が守られたあとの次のステップとして、自宅に戻るのか・避難所で生活をするのか・どこかに身を寄せるのかという、避難生活の計画を考えます。
避難生活の計画を立てるためには、第一に、ご自身の生活環境をしっかり把握することからはじまります。
そして「ハザードインパクト」への理解が重要になります。たとえば風水害が起きるとします。「川が決壊して水が流れ込んできます。あなたの家は1.5メートル浸水します」というのがハザードマップから得られる情報です。でも肝心なのは「じゃあ、1.5メートル床上浸水すると、私の家はどうなる?私の生活はどうなる?」というポイントで、これがハザードインパクトです。これは行政が流す「1 対 多」の情報には含まれないので、自分で考えなくてはならないところになってきます。
指定避難先は小中学校だけれど「そこに本当に行きたい?行く必要がある?」と考える。床上浸水しても、マンションの3階に住んでいるのであれば、ライフラインに問題がなければ「じゃあ第一候補は自宅での避難生活」、第二は、もし高台に親戚や知り合いの家があれば「そこに一時的に身を寄せる」になるかもしれません。
自分だけで避難計画をたてるのが難しいと思うのであれば、防災士や市町村の防災危機管理の人など、適切な情報をもっているかたに頼りましょう。
また計画を立ててみたら、一度、実際に避難訓練をしてみることもおすすめします。
個別の避難計画の立てかたについて詳しくは、ぜひこちらもお読みください。
▶︎防災リテラシーって?「私」の避難計画の立てかた
https://bosaivoice.com/professor/1/
子どもに関する物資は?
大きな不安に「オムツが足りなくなること」と「子どもの食事」があります。
子どもは体調に波があって、たとえばお腹を壊して下してしまうと、オムツ1日3枚で足りるところ8枚ほど必要になったりします。
3歳になる上の子が特に偏食なので、ご飯を食べてくれるかどうか、自分で用意する子どもの好物(アンパンマンカレーなど、常温でも美味しい)がなくなってしまった場合に、そういった物資ってリクエストできるのでしたっけ...? 1歳の子の離乳食が切れてしまうのも心配です。
お子さんの年齢によって課題も異なりますが、ミルクやオムツは避難所で入手が困難なものの1つです。離乳食は備蓄としてもたないため、実際にいろんなお母さんが困っているのを目にしてきました。
また、女性に関していえば生理用品。これまで避難所によっては「嗜好品扱い」されてしまい、送り返されてしまった、なんてこともありました。
準備や備えにも限りがありますので、できることとしては「近距離・中長距離」のコミュニティやネットワークをつくっておけるとよいです。
近距離は、同じ避難所にいるかたで、ほかの妊産婦さんやお母さんとコミュニティをつくり支えあえる環境をともにつくること。物資の融通だけでなく、配給の有無や状況などの情報共有をすることも大切です。同じ境遇で助けあえる・支えあえる人がいるのはとても心強いはずです。
中長距離とは、地域の外の人たちとのネットワークです。物資として確保できない、買いにもいけない場合には、地域をまたいでの当事者団体、支援団体、民間企業に相談するなども1つの手です。
とはいえ、災害が起きてからではできることは限られる・難しくなることがあるので、特に近所のかたたちとは普段からあいさつをかけあう程度でも関係性を構築しておくにこしたことはありません。
避難所の生活での不安。誰がいるかわからない
避難所に誰が集まっているかわからなことも、不安要素の一つです。子どもがの目に映る大人たちの姿が、常に健全であるとは限りませんよね、なにかトラウマになるようなことが起こったりしないか...。性被害の危険性についても考えます。
また、子どもがその環境に馴染めるのかも心配です。子どもの機嫌や状態によって、まわりの方たちに迷惑をかけないか、気を揉むと思います。
子どもたちのこともそうですが、女性である自分の身の安全も、やはり気になります。
私は妊娠してから心身ともに波があるので、避難所生活でストレスを抱えること自体が不安です。あとは、センシティブになっている部分も結構あり、衛生面もとても気になるところです。
避難所生活が長引くと、子どもには好ましくない大人同士のやり取りを目にしてしまう、といったことも実際に起きます。なので、プライバシーの確保や、多目的スペースなどを設けて、子どもが自由に過ごせる場所などがあるとよいでしょう。
子どもが夜泣きしてしまったときに、どこに身を置いたらいいかわからずに、寒かろうが真っ暗な避難所の駐車場であやしていたという話も聞きますが、安全ではありません。
避難所運営において、身の安全を守るための対応を、実際の実施例とあわせていくつか紹介します。
ルールを“見える化”
「こういうことはやっちゃダメ」「こういう発言はハラスメントになります」といったルールを決めて、それらを紙などに書いて、避難所の見えるところにいつくか貼っておくだけで抑止力になります。
ナースコールを設置
一人ひとりに防犯ブザーではなく「ナースコール」を配った事例も。女性だけでなくみんなに配り、要は「何かあったら呼んでね」とする。実際に「防犯ブザーだと、一緒に避難している地域の人を疑っているみたいな感じで、気が咎める」という意見があったそうです。ナースコールだと「身の危険だけでなく、たとえば発作など、なにか困ったときにはいつでも誰でも押していいんだよ」というかたちで案内できる。抵抗感をやわらげ、不要な軋轢を回避できます。
自然な“監視”をつくる
たとえば、体育館の外のトイレに行くときは集団でいき、必ず他の人の目があるようにする。あとは、夜でも通路部分を明るくしておく・人の動線を考え、トイレは奥まった場所ではなく人通りが絶えないところに設置するなど。あとは、警備員さんに頼んで常駐してもらうなどもありです。
集団行動
体育館の外のトイレに行くときは集団でいきましょう。
受付を設置
避難所に、受付を設置し誰かしらが常駐することで、施設への不審なアクセスを制御することができます。
自警団を設置
これはおもに、避難所生活というよりはご自宅などでの防犯対策です。定期的に自警団をつくって自分たちの地域を巡回しておくと「きちんと見ている・ケアしている」ということを外向けにアピールすることは有効です。災害時は盗難などが増えますが、巡回していることで「いつ人がくるかわからない」と思わせ、防犯になります。
メンタル面の不安
子どもたちはとにかく体力がすごい。避難所の箱詰め状態ななか、子どもたちのストレスもマックスになると言うことをきいてくれないこともある。親である自分たちのメンタルももつのかなあといった、メンタル面での心配もあります。*
腰痛などもあるので、避難所でどれくらいセルフケアができるのかも想像できないので不安です。自分一人だったらいいのですが、赤ちゃんのことも考えると余計...。避難所のかたとの共同生活をしっかりおくれるのか、とか。
*子どものストレスは、母親のストレス対処資源**を活用して低減されるといわれています。そのため、子どものメンタルケアをするときには、親のメンタルケアも同時におこなう必要があるとされます。
参考文献:
Lahad, M., Shacham, M., & Ayalon, O. (編). (2017). 緊急支援のためのBASIC Phアプローチ――レジリエンスを引き出す6つの対処チャンネル. 遠見書房.
**対処資源とは、ストレスを低減させるための資源のこと。自身が備える資質、ストレス対処に役立つ人、モノ、情報などのことで、私たちは身の周りにあるこういったものに頼りながらストレスを乗り越えているとされます。
避難所といえどもやはり生活の場なので、自分のセルフケアができるような避難所になっているかは、非常に大切です。
まずは避難所の基準に「TKB48」という考えかたがあります(「AKB48」からとっています)。Tがトイレ、Kがキッチン(食事) 、Bがベッドで、これらを48時間以内にちゃんと整えましょう、というものです。これがきちんと提供されてはじめて生活になる。
これが整ったら、避難者であるその地域住民のみなさん自身で生活を改善するアイデアを出していけるとよいです。そのための場づくりも避難所では重要になってきます。
たとえば、みんながちゃんと出てきてご飯を食べられるように「体育館に食堂をつくります。ご飯は食堂で食べよう」とすると、コミュニケーションの場にもなります。人と喋ることはストレス解消に非常によく、情報収集の場にもなるので、そういったコミュニティスペースをつくることは有効です。ちょっと場所を空けて受験生のためのスペースにして、子どもたちが勉強できる場を確保したという工夫例もあります。
また、親御さんが抱える課題の一つに、保育園・学校がストップするため、子どもを預ける先がないために常に面倒を見なくてはならず、家の片付けなどの生活再建が遅れていく、などもあげられます。NPO団体によっては、避難所に子どもが遊べるスペースと時間を設け、その間に親御さんが生活再建のために作業できるようにする、といった支援の取り組みもあります。
どうやったら暮らしやすくなるのかをみんなが柔軟に考え、意見を出し合う場づくりも重要です。多様な意見が入れる余地をもてると、より多くの人に対して健康が維持できて住みやすい避難所、居所として成立する避難所にしていけると思います。
こういった改善には、日々、生活をつくっている女性の視点がとても重要です。避難所を殺伐とさせず、一人ひとりがセルフケアができるような場所づくりは、その地域での暮らしに一番モチベーションをもてる住民のみなさんだからこそできることも実際には多くあります。
ADVICE VOICE

松川杏寧 准教授
1984年生まれ。同志社大学大学院社会学研究科で博士の学位取得後、人と防災未来センター、防災科学技術研究所を経て現職。
専門は犯罪社会学、福祉防災学。2011年の東日本大震災までは環境犯罪学による犯罪予防について研究していたが、3.11以降災害の分野へ。
地域住民による犯罪予防や災害時要配慮者の防災対策、避難所研究など、地域コミュニティや脆弱性の高い人々を主な研究の対象としている。